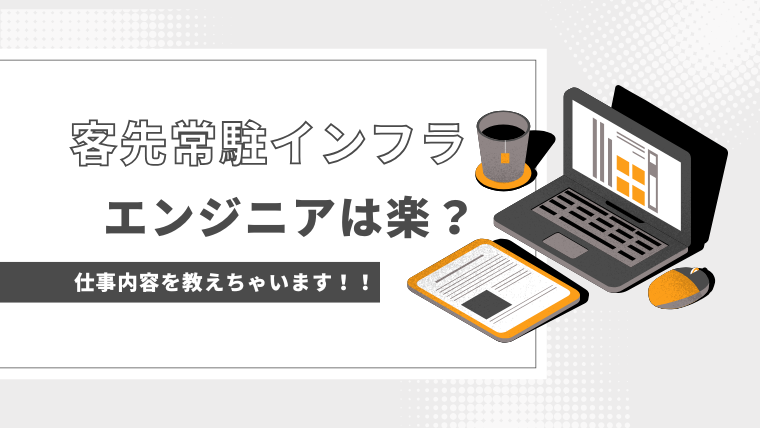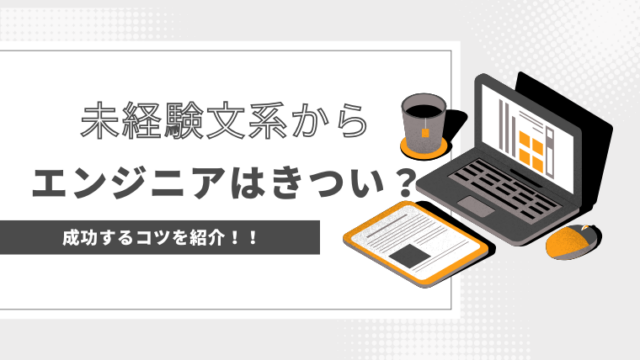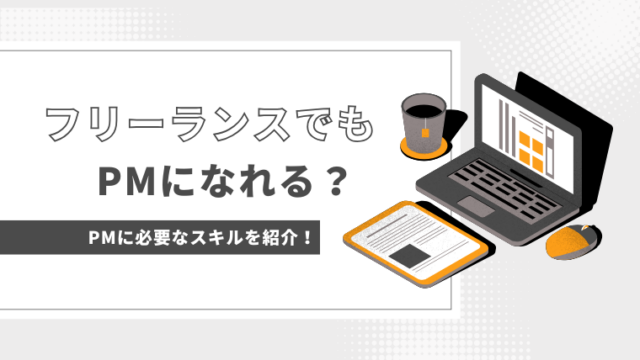未経験からIT業界に転職すれば、リモートワークもできて今より楽に稼げるかも…と思ってたんですけど、実際に求人を探してみると未経験OKの案件ってほぼないんですよね、
ようやく内定が出たのは客先常駐のインフラエンジニアだったんですけど…これって本当に楽に働けるんですかね?結局また長時間労働になるんじゃないかって不安なんですよね。
でも、この記事を読めば客先常駐インフラエンジニアの働き方について知ることが出来るのでおススメです!なぜなら、この記事は現役客先常駐インフラエンジニアの私が書いているからなんです。
目次
1.客先常駐インフラエンジニアは楽すぎる!?
「客先常駐インフラエンジニアは楽」という話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?
実際のところ、客先常駐のインフラエンジニアは本当に楽なのか?
結論から言うと、それは現場次第です。
私は現役の客先常駐インフラエンジニアとして働いており、これまで複数の現場を経験してきました。本記事では、その経験をもとに、客先常駐インフラエンジニアの実態や一日の流れについて紹介します。
1-1.客先常駐とは
客先常駐とは、自分が所属する会社ではなく、お客様の会社に出向いて業務を行う働き方です。
基本的に、社内のルールや業務の進め方は自社ではなく、お客様先の基準に従います。
客先常駐のメリット
- さまざまな企業の環境で働ける
案件ごとに現場が変わるため、1社に縛られず、いろいろな企業のインフラ環境を経験できます。 - 人間関係がリセットされやすい
一つの現場に長くいる人もいますが、プロジェクトが終われば次の現場に移ることも多いため、人間関係に悩みにくい点も魅力です。
1-2.インフラエンジニアの仕事内容
客先常駐のインフラエンジニアはどんな仕事をするのかを紹介します。
基本的には、客先だからといって業務内容が特別変わるわけではありません。主に設計構築業務と運用監視業務に分かれます。
設計・構築業務
サーバやネットワークの設計、構築を行う業務です。
私が初めて経験した現場では、お客様先のプロパー(正社員)と一緒に以下の業務を担当しました。
- 要件定義の書類作成
- 設計書の作成
- サーバ構築
運用・監視業務
既存のシステムを維持・管理する業務です。現在の現場では、設計・構築業務に加えて、以下の業務を担当しています。
- バージョンアップ作業
- アラート対応
運用監視業務は比較的ルーチンワークが多く、未経験でも入りやすいという特徴があります。
1-3.客先常駐インフラエンジニアの一日
現場によって様々ですが、参考に私のきゃさき常駐インフラエンジニアとしての一日を紹介します。
9:00:業務開始
現在はリモートワークのため、出社がないため起きてすぐ仕事を始められます。
9:00:アラート対応開始
業務開始後はすぐに、前日分のアラート対応を行います。アラートの量が多かったり、問い合わせが必要なものが出ると、一日がかりの日もあります。
12:00:お昼休憩
大体午前中にはアラート対応が片付きお昼休憩に入ります。
13:00:設計構築業務開始
午前中に行っていた業務は定型業務で、ここからWBSの業務を開始します。パラメータシートの作成やサーバ構築、またはテストなどの業務をこなします。
15:00:お昼のアラート対応
この時間になると、一度業務中に出たアラートの対応などを行います。また、問い合わせを行っていた案件の本番作業などを行う日もあります・
17:00:設計構築業務続き
アラート対応が終わると、設計構築業務に戻ります。アラートの対応をしつつ、WBSを順守して作業を行うのが一番大変だと実感しています。
18:00:退勤
トラブルやWBSでの遅延がなければ定時で上がります。アラート対応を一日行っていた場合は、残業などをして遅れ分を取り返す作業を行います。
これはあくまでも一例ですが、私は設計構築業務と運用保守業務を兼務しており、普通の現場であれば、設計構築業務/運用保守業務で担当が分かれていることがほとんどだと思うので、自分の作業にコミットしやすいと思います!
2.客先常駐インフラエンジニアが楽すぎる理由
「客先常駐のインフラエンジニアって本当に楽なの?」という疑問を持つ方も多いと思います。
もちろん、すべての現場が楽とは限りませんが、比較的負担が少ない環境もあるのは事実です。では、具体的にどのような点が「楽」と感じるのか紹介したいと思います。
2-1.定型的な業務が多い
客先常駐のインフラエンジニアは、毎日同じ業務を繰り返すことが多いです。特に運用・監視業務が中心の現場では、決まった手順に沿って作業を進めるケースがほとんどです。
例えば、運用業務では以下のような作業が発生します。
- アラート対応
- 定期的なシステムチェック
- バックアップの確認
もし、今まで対応したことのないアラートが発生した場合は、サポート窓口へ問い合わせたり、調査を行うこともありますが、基本的には過去のナレッジが蓄積されているため、それを参考にすれば対応可能です。
そのため、作業の大部分は定型化されており、難易度が高い業務は少ないというのが特徴です。私の現場でも、redmineというツールを使用して、これまで受信したアラートの対応履歴を管理しているため、案件参画後すぐに業務に入れました。
2-2.手順書ベースの作業が多い
インフラエンジニアは、運用しているサーバやネットワーク機器を扱うことが多く、作業ミスが許されないため、手順書(マニュアル)に沿って業務を進めます。
例えば、
- システムのバージョンアップ作業
- 定期的なサーバメンテナンス
- 新規ユーザーの追加
といった業務は、事前に決められた手順書があるため、未経験者でも手順書通りに進めれば対応できる仕組みになっています。
そのため、「難しい作業を自分で考えて進めるのが苦手…」という人でも、手順書を確認しながら作業を進められるので、負担が少なく働ける環境が整っていることが多いです。
さらに、作業の属人化を防ぐ意味も込めて私は本番作業を行う際には必ず手順書を作成し、作業証跡を残すようにすることを心がけています。これにより、私が不在でも私以外の人が作業できるような体制を作ることを心がけています。
2-3.自動化技術の活用
近年では、インフラ業務の自動化が進んでおり、単純作業の負担が大幅に軽減されています。
例えば、サーバ構築の際にはAnsibleやスクリプトを活用することで、手作業を最小限に抑えた作業環境になっています。
実際に、私が経験した現場でも、
- サーバのセットアップをAnsibleで自動化
- 同じ設定を複数のサーバに適用する際はスクリプトで一括実行
といった仕組みが導入されており、未経験者でもスクリプトを実行するだけで構築作業ができる環境になっていました。特にエージェントソフトなどは複数のサーバにインストールする必要があるため、スクリプトなどで自動化できるようにするのが良いと思います。
このように、作業の標準化・自動化が進んでいる現場では、経験が浅くてもAnsibleやスクリプトを実行するだけで、サーバの構築などができる体制が整っています。
3.客先常駐インフラエンジニアのデメリット
客先常駐のインフラエンジニアは「楽」と言われることもありますが、その一方でデメリットも存在します。特に、スキルの習得やキャリアの面での課題を感じる人が多いのが実情です。
ここでは、客先常駐インフラエンジニアとして働く際に直面しやすいデメリットを紹介します。
3-1.下流工程の業務が多い
客先常駐のインフラエンジニアは、下流工程の業務が中心になりがちです。
システムの設計や構築といった上流工程は、基本的に客先の正社員(プロパー)が担当することが多いため、常駐エンジニアは運用・監視・保守といった業務がメインになります。
このような環境では、
- 設計や構築の経験を積める機会が少ない
- 手順書通りの作業ばかりで、自分で考えて動く機会がない
といった状況になり、スキルアップが難しくなってしまうことが多いです。
私も前職の現場で協力会社さんを雇っていましたが、その方は3年目にもかかわらずテスト工程しかやったことがないとおっしゃっていました、、、
「将来的に設計や構築をやりたい」と考えている人にとっては、キャリアの成長が遅れやすい点が大きなデメリットと言えます。
3-2.客先で放置されてしまうことがある
受け入れ体制が整っていない現場では、仕事を振られずに放置されてしまうことがあります。
例えば、
- 業務の引き継ぎが不十分で、何をすればいいのかわからない
- チームのメンバーが忙しく、指示がもらえない
といった状況になり、ただ出社しているだけで時間が過ぎてしまうケースもあります。
実際に、私自身も受け入れ体制が不十分な現場で、何も指示がなく時間を持て余している人を見たことがあります。
放置されると、業務経験が積めないだけでなく、
「このままでいいのか?」と不安になる
モチベーションが下がる
といった精神的なストレスも大きくなります。
こうした状況に陥らないためには、自分から積極的に仕事を探したり、質問をする姿勢が重要です。
3-3.夜勤や休日出勤がある
客先常駐のインフラエンジニアは、24時間365日稼働しているシステムを担当することが多いため、夜勤や休日出勤が発生しやすい傾向にあります。
特に、下流工程である運用・保守業務に関わると、
- 夜間の障害対応
- システムメンテナンスのための休日作業
といった勤務が求められることがあります。
夜勤や休日出勤があると、休日が減り、プライベートの時間が取りにくくなる
といったデメリットがあります。
すべての現場で夜勤があるわけではありませんが、常駐先の業務内容をよく確認せずに入ると、予想以上に負担の大きい働き方になる可能性があるため注意が必要です。
3-4.給与が平均より安い
客先常駐のインフラエンジニアは、下流工程を担当することが多いため、給与水準が低めになりがちです。
特に、設計や構築を経験できないまま運用・保守の仕事を続けていると、
- スキルが伸びにくい
- 市場価値が上がらない
- 転職しても給与があまり上がらない
といった状況に陥る可能性があります。
実際に、客先常駐エンジニアの中には、
「長年働いているのに、給料がほとんど上がらない…」
と悩んでいる人も少なくありません。
そのため、給与を上げたい場合は、設計・構築ができるエンジニアを目指すことが重要です。
4.客先常駐インフラエンジニアのキャリアパス
客先常駐のインフラエンジニアは、働きやすい反面、下流工程の業務が中心でスキルアップしづらい、給与が伸びにくいといったデメリットがあります。
そのため、長期的なキャリアを考えると、意識的にスキルを伸ばし、市場価値を高める必要があります。
ここでは、客先常駐エンジニアがキャリアアップするための具体的な方法を紹介します。
4-1.資格を取得する
スキルアップの第一歩として、IT関連の資格を取得するのは非常に有効です。
特に、運用・保守業務が中心の環境では、業務経験だけでは設計・構築スキルを身につけにくいため、資格取得を通じて体系的な知識を学ぶことが重要です。
その中でおすすめのなのがAWSの資格です。現在様々な企業でクラウド化が進んでおり、クラウドエンジニアの需要が非常に増しています。その中で、客先常駐インフラエンジニアの方にピッタリな資格を紹介します。
AWS Certified Solutions Architect – Associate
AWS Certified Solutions Architect – Associate通称AWS SAAはAWSの設計に関する資格です。こちらを取得することで、AWSの設計に関する力を証明することが出来ます。
AWS SAAの勉強方法については以下の記事を参考にしてみてください。

AWS Certified SysOps Administrator – Associate
AWS Certified SysOps Administrator – Associate通称AWS SOAはAWSの運用に関する資格です。こちらを取得することで、AWSの運用に関する力を証明することが出来ます。AWS SOAの勉強方法については以下の記事を参考にしてみてください。
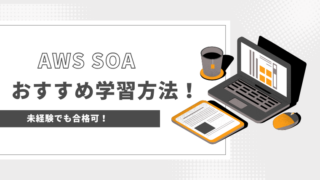
AWS SAAは設計構築工程にキャリアアップしたい人は、ぜひ取得を目指してみてください!AWS SOAは運用業務を経験した方にとっては取っ付きやすいと思いますので、取得することで、AWSの運用保守もできることを証明できるので非常におススメです!
4-2.客先常駐ではない会社に転職する
客先常駐の環境では、業務内容やスキルアップのペースを自分でコントロールしづらいことが多いため、自社内で設計・構築を行う企業に転職するのも有効な選択肢です。
また、以下のような企業に転職することで、設計構築の経験が積めるほか、給与Upやキャリアの選択肢が広がることが予想されます。
自社サービスを持っている企業
自社サービスサービスを持っている企業に転職することは非常におススメです。自社サービスを持っている会社であれば、設計・構築といった上流工程を担当することが可能です。また、自社の成長とともにキャリアアップも可能になっています。
SIer(システムインテグレーター)
自社サービスを持っている企業に続き、SIもおすすめです。SIは、お客様に向けにシステムを開発・提供する企業です。ここでは構築といった自分自身で手を動かす機会は、自社サービスを扱う企業よりは減りますが、要件定義や設計業務を中心にキャリアを積むことが出来ます。
クラウドベンダーや MSP(マネージドサービスプロバイダー)
クラウドベンダーも同様におススメです。現在、様々な企業がクラウド化に舵を切っています。そのため、クラウドを使用して設計構築する機会が格段に増えることが予想されます。クラウドを使用したキャリアップを目指すことが可能です。
上記のような会社に転職を目指す場合は、資格取得や個人での技術習得を進め、即戦力としてアピールできるスキルを身につけることが大切です。
4-3.上流工程を経験する
客先常駐エンジニアのままでも、意識的に上流工程の経験を積むことでキャリアアップは可能です。
設計構築ができる案件に入れてもらう
客先常駐エンジニアであっても、設計構築の案件に入ることは可能です。私も初めて入った案件では、設計構築業務を経験させていただきましたし、現在も運用と兼務ですが設計構築業務を行っています。
こちらに関しては会社の営業力などが関わってきますが、自社の方に積極的に設計構築案件に入りたい旨を伝えることで、実現が可能になると思います。
自宅でサーバを構築してみる
設計構築ができる案件にどうしても入れない場合は、自宅でサーバ等の構築をやってみることをおすすめします。自宅に物理サーバを設置するのは難しいですが、VirtualBoxなどを使用して、WindowsやLinuxサーバを構築し経験を積むことが出来ます。
個人でサーバ構築を行うことで、構築力の証明にもなりますが、自分自身で自己研鑽をできる証明にもなりますので、ぜひ行ってみてください。
5.まとめ
今回は、客先常駐インフラ園児には楽なのか!?について解説しました。
結論、現場によります!
ただ、客先常駐インフラエンジニアは定型作業が多いことや、業界として自動化が進んでいるので、未経験の方でも安心して業務に着けると思います。
今後も、インフラ系の情報を発信していきたいと思います。 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。